| 日 時:平成17年9月17日(土) 場 所:羊ケ丘レストハウス(札幌市) 担当者:福井事務局次長 |
| 大正6年、札幌と滝川に種羊場が作られ、その後ジンギスカンが誕生しました。北海道の伝統的な食文化であり、観光の代表格であるジンギスカンは北海道遺産に認定されています。北海道民として独自の食に対する理解を深め、全国へ発信するために7月に滝川でジンギスカンサミットが開かれ、今回はそれに引き続き、札幌での開催となりました。9月16日(金)の前夜祭から始まり、フォーラム、ご当地クイズ、オリジナル食べ方コンテスト、新メニュー発表など9月19日(月・祝)までジンギスカンの普及に関わる多くのイベントが展開されました。 |  |
| 9月17日は、今後のジンギスカン普及をどう考えていくべきなのかを提言するための「ジンギスカンフォーラム」に参加してきました。 |
 |
基調講演は谷一之先生です。北海道遺産推進協議会に所属するばかりではなく下川町の地域学「しもかわ学会」の立ち上げにも大きく貢献されています。ジンギスカンが北海道遺産に認定されたのをきっかけとして、これからの期待と応援だけではなく、羊肉の大半が輸入されている状況を転換し、北海道産の羊肉でジンギスカンを楽しむことが北海道の食文化として更に発展するキーワードではないかと提言されていました。 |
 |
 |
その後のパネルディスカッションでは、麻田副知事や小澤副市長が参加されジンギスカンの歴史から、効用、北海道の食文化としてどのように道民が向き合っていけば良いのかなど様々な提案が出されました。 |
| 西区役所前を出発し、一路八軒会館までの約1キロを、先頭からバトンチーム、鼓笛隊、屯田兵、地元の参加者、そして私たちも最後尾に参加させていただきました。 |
| 当日はフォーラムだけではなく、3種類のラム肉を自分で選び味わうなど、ジンギスカンを思う存分堪能することができました。ちなみに写真の肉は長沼産のラム肉・塩ラム肉・たれラム肉の3種です。 | 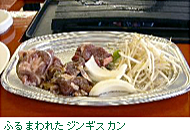 |
| 食堂は、ジンギスカンに舌鼓を打っているお客さんで賑わいました。道外から来ている方も多かったです。あいにく雨天だったため屋外の売店は開かれてはおりませんでしたが羊肉を使ったカレーやその他のメニューも楽しめるそうです。 |  |
| ジンギスカンは北海道人が羊肉の食べ方を工夫し、今の形まで育てた郷土料理です。基本的には、ジンギスカン鍋を用いて羊肉を焼いて食べる料理ですが、実際には、肉の種類にはじまり、鍋の種類、焼き方、たれの付け方、焼き野菜の種類など、各家庭により様々です。ジンギスカンの歴史は以外に浅く、大正時代からです。現在のジンギスカンが普及したのは、さらに最近のことであり昭和20年代後半です。しかし、昭和30年代には、家庭で食べるだけでなく、小・中学校の炊事遠足、キャンプやお花見など、野外で食べる料理の定番となりました。 今回のフォーラムに参加して、ジンギスカンが北海道遺産への認定とジンギスカン食普及拡大プロジェクト開催をきっかけに、道民はもとより更に多くの地域の人々の食文化として愛されるメニューに成長できる可能性を感じました。 |
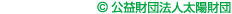 |